

トイレつまりは、突然起こるように思われることもありますが、たいていは前兆となる症状があります。この前兆をあらかじめ知っておき、症状に早く気づくことで、ご自分で詰まりを解消できる確率が高まります。普段と違うと感じることがあった際は、注意深く観察してみてください。
トイレの使用後に何らかの違和感を抱いたときは、詰まりの前兆かもしれません。たとえば、水の流れが悪い、水の勢いが弱い、流した後いつまでも水位が高い、水を流すと異音が聞こえる、このような場合は特に注意が必要です。
便器内に常にある封水は、下水からくる臭いを封じる働きをもっています。掃除しているのにいつもとは違う悪臭、特に下水臭が気になるという場合は、排水口につまりがあるサインかもしれません。詰まりによって封水が減り、悪臭がすることがあるためです。
トイレの詰まりがちな場所と、三大原因をおさえておけばいざ詰まってしまったときでも対処がしやすくなります。
トイレが詰まりやすいのは、主に2箇所です。
1つ目は便器の奥にある「せき」という部位は排水路への通路にあり、急なカーブ状をしています。そのため重たいものや大きいものがつまりやすくなっている形状でもあります。
もう1箇所は、「せき」を越えた排水路の下水に流れる前の部分です。そこにも配管が狭い部分があり、水に溶けないものが溜まりやすく、つまりやすい部分だと言えます。
トイレに異物を流すことは、つまりを引き起こす原因になってしまいます。
毎回流すトイレットペーパーは水溶性ですが、つまる原因になることがあります。1度にたくさん流すことは避けましょう。ティッシュペーパーは水に溶けにくく、トイレ用ではありません。トイレットペーパーの代わりとしては不向きです。
トイレのクリーナーシートは、説明書きにトイレに流しても大丈夫だと記載があっても、一度に流し過ぎると溶けきれず、つまりの原因になることがあります。ごみとして廃棄するか、複数枚使用するときは少しずつ流すとよいでしょう。
うっかり落として流してしまいがちなナプキン、おむつ、ペットシートなどは、経血や尿などを吸い込む性質があります。トイレに落としてしまうと水を大量に吸い、体積が増えることでつまりの原因となります。お尻拭きシートも本来水に溶けにくい成分でできています。
他にも固形物(スマホや財布、ライター、カイロなど)、ペットのトイレ用の砂、食べ残しや嘔吐物なども、水がスムーズに流れるのを阻害します。
もう1つは、水の圧力が不十分であることです。大と小のレバーの使い分けが適当でないことも原因となります。
基本的に、大のレバーは排便時に、小のレバーは排尿時に使用します。これらは使用する水量が異なるため正しい方を使用するようにしましょう。
大レバーを使うべき状況なのに節水のために小レバーを使うと、しっかりと流しきれずトイレの流れを悪くすることがあります。節水をすることは環境には大切ですが、レバーの使い分けは適切に行いましょう。
有名な方法のため一度は耳にしたことがある方も多い節水方法としてトイレのタンクに水を入れたペットボトルやビンを沈めておくという方法があります。
この方法ではタンクに溜まる水を強制的に減らすことで使用する水量を減らして節水を行なうという方法で、節水の観点だけで言えば節約になります。しかし、必要水量に満たない状態で使用をするのは当然トイレつまりを助長することに繋がります。
また、この方法の問題点はトイレつまりだけでなく故障を引き起こす要因にもなる点で、タンク内にあるボールタップや浮き玉、フロート弁などの部品を壊してしまう可能性もあります。
万が一トイレが故障してしまうと節水によって節約できた金額以上に修理費用が必要になり、結果として損してしまうことが考えられるので、自宅のトイレでおこなているようであれば早めに撤去しましょう。

本項ではトイレが詰まったらまず試していただきたい、解消法を5つご紹介します。
まず、便器底の封水がたくさん溜まっていた場合は、手桶などを使ってあらかじめ水を減らしてください。封水の水位が排水口にあたるぐらいまで減らすのがポイントです。
そして、バケツや手桶、ペットボトルなどに入れた水を勢いよく便器に流し、その水圧も利用して原因となっているものを溶かします。流しても水位が上がらなくなれば、溶け始めた合図ですので、レバーで水を流してみましょう。
水だけでなく空気も一緒に加えるように注ぐとさらに効果的です。そのためには水を一気に加えず、高めの場所から少しずつ注いでください。
この方法は、水に溶ける性質をもったトイレットペーパーのような紙がつまった場合に効果があります。
これも前述と同様の水に溶ける性質をもった紙類がつまっている場合に、ぜひ試していただきたい方法です。水よりも早く溶かすために、ぬるま湯を使用します。
効果が高いだろうと考えて熱湯のように温度が高いお湯を注ぐと便器にダメージを与えてしまいますので、水温は50度までにとどめましょう。流し込む際は、バケツなどで水を注ぐのと同様に高い場所から流してください。
ぬるま湯を注いだ後は30分程度放置し、再度ぬるま湯を加え便器内の封水の変化をチェックします。便器に溜まる水が通常時の量になるまで、繰り返しチャレンジしましょう。
より溶けやすくするために、市販の洗浄剤や、重曹とお酢を1対2の割合で加えるのも同様の効果が期待できます。
昔ながらのゴムのラバーカップ(通称:スッポン)を使う方法です。この方法は水に溶けやすいものだけでなく水に溶けにくいものにも有効です。
ビニールシート、または大きめのゴミ袋を便器の排水口にかぶせて、中央に穴をあけラバーカップが入るようにセットすると、トイレの周りが水浸しになるのを防ぐことができます。ラバーカップを排水口に押し当てて穴をふさいだら、一気に引き抜きます。
これを何度か繰り返し行います。ただし、便器内の封水が多い場合は、あらかじめ通常時の量まで水を減らしてください。
スッポンで何度かトライした後、バケツなどで水を流し水位が上がってこなければ、つまりがとれた合図です。
スッポンの使い方については下記の記事でも詳しく解説していますので併せて参考にしてください。
真空式パイプクリーナーを使用する方法はスッポンで何度か試しても改善されない場合や、固形のものを落とした際にも試したい方法です。スッポンよりも吸引力が強いのが特徴です。
スッポンのときと同様に溜まっている水の量が多ければ前もって水を排出してから、ゴミ袋などを便器にかぶせて使用しましょう。ハンドルは便器の中に入れる前に押しておきます。
水につけた状態で押すと汚水が飛び跳ねますので、注意してください。排水口にカップを密着させ、ハンドルを引きます。これを何度か繰り返して異物を除去します。
ワイヤー式トイレクリーナーは本来排水管の内側を掃除するための器具であることから、少し使い方が難しいというデメリットもあるので、最終手段としてご紹介します。水浸しになるのを防ぐために、ビニールシートかゴミ袋で便器を覆い、中央部に器具を入れる穴をあけて作業します。
ワイヤーをくるくるねじりながら奥へ進め、途中で動きにくくなったら、前後にゆっくり動かすか、ハンドルを回してください。不溶性のものの場合、ワイヤーを使って取り出しましょう。汚物などは押し流すようにします。

トイレの詰まりは自分でなんとかできる場合と、業者に任せた方が良いケースがあるので、ご紹介します。
水に溶ける紙類をつまらせた、時間はかかるが便器内の水が減っていく、封水が増えたままで減っていかない、というケースは自分でもなんとか解消できる可能性があります。まずは前項で紹介した方法を試してみてください。
水溶性の紙類をつまらせたという場合でも水が引く、引かないというのは症状の重さによって変わってきます。紹介した方法を試しても効果がない場合は、悪化してしまう前に早めに業者に相談する方が無難です。
水を含んで膨れるもの(おむつや生理用ナプキン、ペットの砂など)や、その他の固形物を誤って流してしまい、水があふれてトイレ内が水浸しになったという場合は、早めに業者に相談しましょう。
無理に自分でどうにかしようとすると、便器自体が故障し思わぬ出費が発生するという事態にもなりかねません。水が溢れている状態が続くと床や壁に汚水が染みることで内装工事が必要になることもあります。
依頼する水道業者の選び方については下記の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
トイレをつまらせないためには、日頃からの正しい使用が不可欠です。普段から気にかけておきたい注意点を知っておきましょう。
1つ目は、トイレットペーパーを一度にたくさん流さないことです。そして、不溶性のものはトイレに流さないことです。
最近では使った後にそのままトイレに流せることを売りとした掃除用の商品もありますが、本来はトイレに流さないのがベストです。また流すのであれば、少量ずつ流すのが無難です。うまく流れたように見えても、繊維が水に溶けきっていない可能性もあるので、注意が必要です。
2つ目は、何回かに分けて流すことです。たとえば、排便時であれば最初に排泄物を流します。その後、紙を流しましょう。便器自体も節水に注力しているものが増えているので、使用する側もちょっとした工夫をして回避しましょう。
流す水量を減らすことは、節約方法としては有効ですが、トイレつまりを避けるという意味では推奨できません。
トイレつまり対策としては、日頃からつまりの原因を作らないことが1番です。ですが、もしつまってしまったら、原因を明確にすることから始めましょう。またご自分で対処しきれない場合は、早めに業者に相談した方がよいでしょう。深刻化する前に、早めの対処が大切です。
イースマイルでは24時間365日いつでもトイレつまりに対応しています。最短20分で駆けつけ、トイレつまりを解決しますのでまずは電話にてご相談ください。出張料や見積もりは無料です。

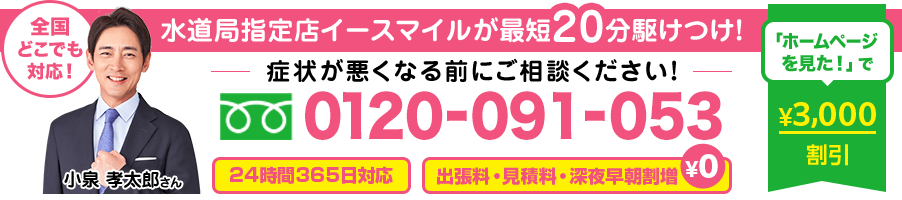

Copyright©株式会社イースマイル【町の水道屋さん】.All Rights Reserved.